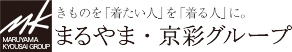着方レッスンコラム着方レッスンコラム
衿芯の入れ方|着崩れ防止で一日中キレイな衿元
2025.06.05

こんにちは!「着たい人を、着る人に」まるやま・京彩グループです。
着物の着付けで特に重要なパーツのひとつが「衿元」です。
しかし、美しい状態を長時間キープするのは意外と難しく、時間が経つとヨレてしまったり、形が崩れてしまったりと悩む方も多いのではないでしょうか。
そんなお悩みを解決してくれるのが「衿芯(えりしん)」です。
この記事では、初心者の方にもわかりやすいように、衿芯の基本的な役割から種類、選び方、入れ方、保管方法、よくある質問までを丁寧に解説します。衿芯を正しく使えば、一日中美しい衿元を保つことができ、着物姿に自信が持てるようになります。
半衿の美しい仕上がりを保つためのコツについても紹介していますので、着付けに自信がない方もぜひ参考にしてみてください。
目次
1.衿芯とは?その役割と種類

衿芯の役割
衿芯は、長襦袢の半衿の内側に差し込んで使う、細長い板状のアイテムです。主に以下のような役割を果たします。
- 半衿のシワを防ぎ、滑らかな曲線を保つ
- 衿をしっかりと支えて、美しい立ち姿を作る
- 汗や皮脂の汚れから半衿を守る
- 着崩れを防ぎ、一日中キレイな衿元をキープする
特に、正絹の長襦袢は柔らかくシワになりやすいため、衿芯を使うことで整った衿元を保つのに役立ちます。夏場は汗をかきやすいため、衿芯が吸湿性を補助し、半衿の汚れ防止にもなります。
衿芯の種類
衿芯には素材や形状にさまざまな種類があります。
- 紙製:紙製の衿芯は通気性が良く汗を吸いやすいため、ムレにくい点が魅力です。価格も手ごろですが、耐久性が低く水に弱いため使い捨て感覚で使うことが多いです。
- プラスチック製:プラスチック製は軽くて丈夫、水にも強いため繰り返し使えますが、静電気が発生しやすいという弱点があります。
- 布製:布製は柔らかく肌触りが良いため着心地重視の方に向いていますが、シワになりやすく乾きにくい特徴があります。
- 金属やワイヤー入り:金属やワイヤー入りのものは、形をしっかり保てるためフォーマルな場に向いています。ただし重さがあることと、やや高価な点がデメリットです。
形状による違い
衿芯の形状もさまざまです。湾曲したタイプは長襦袢の衿のラインに沿って自然なカーブを作り、美しい衿元を演出します。
一方、直線的なタイプは衿の形をしっかりと保つため、着崩れを防ぐのに適しています。
また、幅の広いタイプは衿全体をよりしっかり支えることができ、より整った印象を与えます。さらに、抗菌防臭加工や、襟足の浮きを防止する機能付きの商品も販売されています。
2.衿芯の準備

衿芯の選び方
着物の種類や着用シーンによって、適した衿芯は異なります。
たとえば、振袖や訪問着などフォーマルな着物には、長めでしっかりとしたタイプの衿芯が向いています。一方で、小紋や紬などのカジュアルな着物であれば、少し柔らかめで短めの衿芯も使いやすいです。
浴衣の場合は、軽くて柔らかい素材の衿芯を選ぶと快適です。体型によっても選び方は変わります。
なで肩の方は、先端が少し上向きになっている衿芯を選ぶと衿がきれいに立ち上がります。逆にいかり肩の方は、浮きやすい衿を防ぐために短めの衿芯が適しています。
必要な道具
基本的には特別な道具は不要ですが、以下のものがあると便利です。
- 衿芯
- 着物(または長襦袢)
- 全身が映る鏡
鏡を使うことで、左右のバランスや衣紋の抜き具合など、全体の仕上がりを確認しながら調整ができます。
3.衿芯を入れる上での注意点

衿芯の入れすぎに注意
衿芯を入れすぎると、衿が不自然に張ってしまい、見た目にも違和感が出たり、着心地が悪くなったりすることがあります。また、生地への負担が大きくなり、衿元が傷みやすくなることも。
目安としては、盛夏には薄手の衿芯1枚、単衣や袷には普通の厚さを1枚、冬は厚手の衿芯1枚または2枚重ねが推奨されます。ただし、あくまで目安なので、鏡を見ながら自分に合った厚みを調整することが重要です。
素材に合わせた衿芯選び
正絹の着物には、静電気が起きにくく通気性の良い和紙製や布製の衿芯が適しています。ポリエステルの着物には、プラスチック製も使えますが、静電気が気になる方には和紙製や布製をおすすめします。
夏は通気性を重視し、冬は保温性の高い素材を選ぶようにすると快適に過ごせます。汗をかきやすい方は吸湿性のある素材を選ぶと、衿元を清潔に保ちやすくなります。
4.衿芯の保管方法
衿芯の保管場所
保管時は直射日光や高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管します。タンスやクローゼットが理想的です。
湿気の多い場所に保管するとカビや変形の原因になるため注意しましょう。
保管時の注意点
衿芯はできるだけ平らな状態で保管し、折り曲げたり重いものを乗せたりしないようにします。布で包んだり、専用の袋に入れておくと安心です。
紙製や和紙製の衿芯は乾燥剤を一緒に入れて保管すると湿気対策にもなります。
防虫剤を使用する場合は、衿芯に直接触れないよう注意しましょう。
5.着崩れしない衿元の作り方

美しい衿元をキープするコツ
美しい衿元を保つには、着付け時のポイントと日常動作に注意が必要です。
- 衿芯は左右均等に差し込み、バランスを確認する
- 衣紋をしっかり抜き、首元に自然なゆとりを持たせる
- おはしょりや腰紐はしっかり整え、補正も忘れずに行う
動作も意識すると効果的です。歩くときは小股で優雅に、椅子に座るときは浅く座って背筋を伸ばしましょう。食事中は懐紙やハンカチで衿元を保護し、高い所の物を取るときは腕を高く上げすぎないようにします。
衿元の着崩れを防ぐ便利グッズ
着物クリップや伊達締め、コーリンベルト、補正パッドなどを活用すると、衿元がズレにくく、美しい状態をキープできます。補正パッドで体のラインを整えると、衿芯の安定感も増します。
6.衿芯に関するよくある質問

衿芯は必ず必要?
衿芯は必須ではありませんが、特にフォーマルな場や長時間着物を着るときには、見た目の美しさと快適さの両面で役立ちます。
カジュアルな浴衣では省略することもありますが、衿元のヨレが気になる方にはぜひ使っていただきたいアイテムです。
衿芯が曲がったり折れたりしたら?
軽い曲がりであれば手で優しく直すか、スチームアイロンを使って形を整えることも可能です。ただし、素材によっては熱で変形することもあるため注意が必要です。
折れてしまった場合は、新しいものに交換するのが無難です。
衿芯はどこで買える?
呉服店や着物専門店で購入できます。店員さんに相談しながら選べる点が魅力ですが、やや高価なこともあります。
ネットショップなら手軽に購入でき、価格も比較的リーズナブルです。
大型雑貨店(ロフトや東急ハンズなど)でも一部取扱いがあります。
7.まとめ
衿芯は、美しい衿元を保つための心強い味方です。種類や素材、形状を理解し、自分に合ったものを選ぶことでより快適に、そして長時間美しく着物を着こなすことができます。
正しく使い、丁寧に保管すれば、衿芯は長く愛用できるアイテムになります。ぜひこの記事を参考に、着物姿をより美しく、自信を持って楽しんでください。
まるやま・京彩グループでは、初心者向けの着付け教室を開催しています。
受講前に体験できる無料レッスンもご用意しております。
自分で着物を着てみたい方、イベントに向けて練習したい方、和装の基本からしっかり学びたい方、講師がやさしく丁寧にサポートいたします。少人数制なので、質問もしやすく、手元の動きまでしっかり確認できます。
まずは無料体験レッスンで、あなたのペースで楽しく学んでみませんか?
まるやま・京彩グループでは、着物好きの皆さんがステキな着物ライフを送れるよう、お役立ち情報を発信していきます。
着物の選び方や着こなしについて、もっと詳しく知りたい方は、ぜひまるやま・京彩グループの着付け教室、無料体験レッスンにお越しください。
経験豊富なスタッフが、あなたにぴったりの着物選びをお手伝いします。