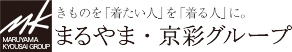着方レッスンコラム着方レッスンコラム
誰でもできる!着付けの衣紋抜きが自然に決まるプロのコツと裏技
2025.06.27

こんにちは!「着たい人を、着る人に」まるやま・京彩グループです。
着物姿を美しく見せる最大のポイントは「衣紋抜き」にあります。
衣紋とは、うなじの後ろにできる衿の開き部分のことで、この部分が自然に整っていると、首すじがすっきり見えて全体の印象が格段に洗練されます。
一方で、「なかなか上手くいかない」「左右が揃わない」「動くと崩れる」と悩む方も多く、初心者には少しハードルが高い部分でもあります。
そこで本記事では、着付けのプロが教える手順や裏技を初心者の方にも分かりやすく、そして再現しやすいようにまとめました。長襦袢(下着)、着物、補正、小物使い、体型調整、そして着崩れ防止まで、衣紋抜きに必要な情報を一気に押さえていきましょう。
目次
1.衣紋抜きが与える印象とその効果

衣紋抜きには、見た目と実用の二面性があります。
- 見た目の効果:うなじが自然に見えることで女性らしさや気品が増し、首が長く見える視覚効果もあります。和装特有の「見せすぎず隠しすぎない」バランスを演出するには不可欠です。
- 実用的な効果:首元に余裕があると呼吸がしやすく、体にも負担がかかりません。特に夏場や長時間着用する場合は、このゆとりが大きな快適さをもたらします。
理想的な抜き加減は「こぶし一つ分」または「指三本分」。ただし、これらはあくまで目安で、体型やTPOに応じて微調整が必要です。
2.抜き加減を調整する3つの基準
以下の3つの基準を意識することで、理想的な衣紋抜きを実現できます。
季節ごとの調整
- 夏(浴衣や単衣など)は涼しげな印象が望ましいため、やや深めに抜きます。
- 冬(袷着物など)は防寒も兼ねて控えめに。衿元をすっきりさせつつしっとりと落ち着いた雰囲気を意識します。
TPOによる調整
- フォーマルな場(留袖、訪問着、結婚式など)では品格を重視し、控えめな衣紋が好まれます。
- カジュアルな場(小紋、紬、浴衣でのお出かけなど)では粋な印象を出すため、少し深めに抜いてこなれ感を楽しむのもオススメです。
年齢や印象による調整
- 若い方:華やかさやうなじの美しさを引き立てるために少し多め。
- 年配の方:落ち着きと品格を表現するために控えめに。
3.長襦袢でつくる衣紋の土台 — コツと手順
半衿のつけ方と衿芯の準備
長襦袢の半衿は、衿全体にシワやたるみがないよう、細かく丁寧に縫い付けることが基本です。特に、衿先から衿肩明きまでをしっかり固定しておくと、着たときに衿が安定し、きれいな衣紋が作りやすくなります。
次に、衿芯選びも大切です。
硬すぎる芯は首に当たって痛く、柔らかすぎると衣紋が崩れやすくなります。首の長さや好みに応じて適度な硬さを選び、差し込む際にはシワやねじれが生じないよう丁寧に入れましょう。
背中心を合わせて長襦袢を羽織る5ステップ
- 長襦袢を背骨の真上に背中心が来るように羽織ります。
- 両袖を通したら、衿を左右の肩に乗せて前で仮合わせ。
- 両手で衿を持ち、背中心を意識しながら後方に引き、肩甲骨の間に自然な空間をつくります。
- 鏡で後ろ姿をチェック。左右対称で、こぶし一つ分の空間があるか確認。
- 胸の下あたりで腰紐を前で結び、衿元を安定させます。
この一連の流れがスムーズにできると、衣紋抜きの基礎がしっかり身につきます。
4.着物を重ねるときの衣紋調整

長襦袢で整った衣紋を崩さないように、着物を着るときにも丁寧な操作が必要です。
- 着物を羽織るときは、背中心を長襦袢に重ねるようにします。
- 衿を長襦袢の衿に沿わせながら後方に引き、衣紋を自然に収めます。
- 右手で上前、左手で下前を持って整え、半衿が適度に見えるように調整。
- 鏡で横から見たとき、着物と長襦袢の衿が一体となった自然なカーブを描いていればOKです。
- おはしょりや帯を整える際にも、背中のシワが衿に影響しないか確認しつつ進めます。
5.補助アイテム&裏技で衣紋を長持ちさせる

衣紋抜き(補正具)の活用
市販されている「衣紋抜き」は長襦袢の背に縫い付けるタイプや差し込むタイプがあり、紐付きなら前で結ぶだけで理想的な衣紋を簡単にキープできます。初心者でも失敗が少なくなる便利アイテムです。
コーリンベルトで衿元固定
コーリンベルトには衿先をクリップで留め、そのゴムが背中中央を押さえる仕組みがあります。これにより、着崩れしやすい衣紋部分をしっかりキープできます。
6.体型別・衣紋抜きの補正術
人の骨格や首の長さによって、衣紋の見え方は大きく変わります。
- なで肩の方:衣紋が抜けすぎがちなため、背中に薄手のタオルを入れて肩線を整えると良いです。
- いかり肩の方:衣紋が詰まりやすいので、補正は控えめにして、衿を広めに抜くとバランスがとれます。
- 首が長い方:やや深めに抜いてもスッキリ見えますが、抜きすぎには注意。
- 物首が短い・太めの方:浅めに抜いて首元をすっきり見せるのが効果的です。
- 両腕を上げ下げしても衣紋が浮かないか?
- 座ったり立ったりしても形が崩れないか?
- 歩いているときに左右非対称になっていないか?
- 鏡で後ろ・横・正面を見て確認
- 衣紋が抜けすぎる:紐をきつめに締める、補正具を使用する、背中にタオルを入れるなど。
- 抜きが足りない:衣紋を最初からしっかりと引く、補正をやや減らす、紐を緩めに結ぶ。
- 左右が揃わない:背中心がずれていることが多いので、鏡で確認しながら再度整える。
- 崩れて元に戻る:補助具を追加する、帯締めも確認する、おはしょりや帯の位置を再調整する。
7.着崩れを防ぐ最終チェック

衣紋が時間とともに崩れないよう、着付け後に以下のチェックをしましょう。
もしズレがあれば、帯をゆるめて衣紋を再調整するか、仮留め用のクリップで固定してから帯を締め直すとスムーズです。
8.よくある失敗とその対処法
9.まとめ
衣紋抜きは着物姿の美しさを大きく左右する重要な要素です。しかし、少しコツを覚えるだけで、誰でも自然で品格ある衣紋を完成させることができます。
この記事でご紹介した長襦袢での手順、着物の重ね方、補助アイテム、体型別の工夫、そして着崩れ防止の最終チェックをしっかりマスターすれば、自信をもって着物ライフを楽しめます。
これから着付けを始める方も、すでに着付けに慣れている方も、ぜひ「衣紋抜き」に向き合ってみてください。それだけで着姿は一段と美しく、印象的になります。
まるやま・京彩グループでは、初心者向けの着付け教室を開催しています。
自分で着物を着てみたい方や、イベントに向けて練習したい方、和装の基本をしっかり学びたい方にぴったりです。経験豊富な講師が、やさしく丁寧にサポートしますので、安心して学べます。
少人数制なので、気軽に質問でき、手元の動きもしっかり確認できますよ。
まずは無料体験レッスンで、あなたのペースで楽しく学んでみませんか?
まるやま・京彩グループでは、着物好きの皆さんがステキな着物ライフを送れるよう、お役立ち情報を発信していきます。
着物の選び方や着こなしについて、もっと詳しく知りたい方は、ぜひまるやま・京彩グループの着付け教室、無料体験レッスンにお越しください。
経験豊富なスタッフが、あなたにぴったりの着物選びをお手伝いします。