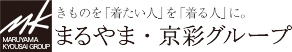着方レッスンコラム着方レッスンコラム
着付けのさらし完全ガイド!種類・巻き方・選び方からお手入れまで徹底解説
2025.06.11

こんにちは!「着たい人を、着る人に」まるやま・京彩グループです。
着付けに欠かせないさらし。種類が多く、どれを選べばいいのか迷っていませんか?
この完全ガイドでは、モスリンや和晒など、着付けに使うさらしの種類やそれぞれの特性、役割、胸元や腰回りといった部位別の巻き方、素材・長さ・幅といった選び方のポイント、そしてお手入れ方法までを徹底解説します。
この記事を読めば、自分にぴったりのさらしを見つけ、着崩れを防ぎ、快適な着心地を実現できるようになります。
さらしを使いこなして、美しい着姿を目指しましょう。
目次 [hide]
1.着付けに使うさらしの種類

着付けに使うさらしには様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。用途や季節、着るものに合わせて最適なさらしを選ぶことが、着崩れを防ぎ、快適に過ごすための重要なポイントです。
主な種類は以下の通りです。
- モスリン:通気性と吸湿性に優れ、肌触りが良いため、特に夏の肌着として最適です。薄手で乾きやすいため、夏の着物や浴衣、襦袢の下に使うと快適です。
- ネル:起毛された綿織物で、保温性が高く、寒い季節に適しています。冬場の肌着や着物の下に重宝します。寒い時期の防寒対策に最適な素材です。
- 晒木綿:丈夫で吸湿性・通気性が良く、価格も手ごろで、オールシーズン使用可能です。普段使いに便利で、煮沸消毒も可能なため、清潔に保ちやすいです。
- 和晒:伝統的製法で仕上げた上質な晒木綿で、柔らかく滑らかな肌触りが特徴です。高級感があり、フォーマルな着物や浴衣に適しています。繊細な肌の方にもおすすめです。
2.着付けにおけるさらしの役割

着付けにおいて、さらしは様々な役割を果たし、美しい着姿を作り上げる上で欠かせないアイテムです。主な役割は以下の3つです。
肌着としての役割
さらしは、肌に直接触れる最初の衣類として、肌着の役割を果たします。汗を吸収し、着物の汚れを防ぎ、肌への負担を軽減します。
特に夏場は、吸湿性・通気性に優れたさらしが快適な着心地をもたらします。また、冬は保温性を高める効果も期待できます。
補正具としての役割
着物は平面的な構造のため、身体の凹凸を滑らかに補正することで、美しいシルエットを作り出します。
さらしは、体型に合わせて自由に巻くことができるため、理想的なボディラインを作り、着崩れを防ぐための補正具として重要な役割を担います。
バストやヒップのボリューム調整、ウエストのくびれ作りなど、様々な箇所の補正に活用できます。
汗取りとしての役割
着物は重ね着をするため、特に夏場は汗をかきやすくなります。
さらしは吸湿性に優れているため、汗を吸収し、着物への汗染みを防ぎます。
また、汗を吸ったさらしを交換することで、常に清潔な状態を保つことができます。着物や長襦袢を汗から守り、清潔に保つ役割も担っています。
3.さらしの巻き方

さらしは胸元や腰回りなどの補正に使われ、体型や着物に合わせた巻き方が大切です。
胸元の補正
胸のボリュームを抑えたり、足したりするためにさらしを活用します。
- 和装ブラ使用時:上からさらしを滑らかに巻いて固定。きつめに巻くと抑え、緩め+タオルでボリューム調整。
- 未使用時:胸の上から斜めに巻き、背中で交差。数回繰り返して平らに整える。
腰回りの補正
着崩れ防止や美しいラインづくりのために行います。
- お腹周り:腹巻のように巻き、下腹部を持ち上げるようにするとすっきり。
- ヒップ:下から斜めに巻き上げてウエストで固定。パッド使用時はその上から巻く。
巻き方は体型や着物に応じて調整し、自分に合った補正を行いましょう。
4.さらしの選び方
着付けに使うさらしを選ぶ際には、素材、長さ、幅の3つのポイントを考慮することが大切です。それぞれのポイントについて詳しく解説します。
素材で選ぶ
さらしは季節や使用目的に応じて選ぶことが大切です。
通気性が良く、汗をかきやすい季節に最適な素材(モスリン)、寒さをしっかり防ぐ保温性の高い素材(ネル)、また肌への優しさやフォーマルな場面での使用が求められる場合には和晒を選ぶのがポイントです。
長さで選ぶ
さらしの長さは用途に合わせて選びましょう。補正を行いたい部分に合わせて長さを調整することが大切です。
胸元やお腹周りの補正に使う場合は短めのものを、腰回りや全体的な補正が必要な場合は長めを選ぶと便利です。
一般的なさらしの長さは9m、10mですが、それ以外の長さも販売されています。
複数の用途で使用することを考えている場合は、長めのさらしを購入し、用途に合わせてカットして使用する方法もおすすめです。事前に必要な長さを確認しておきましょう。
幅で選ぶ
さらしの幅も、用途によって使い分けると便利です。幅の狭いさらしは細かい部分の補正に、幅の広いさらしは大きな部分の補正に適しています。
一般的なさらしの幅は30cm~35cmですが、幅広タイプや幅狭タイプも販売されています。
初めてさらしを購入する場合は、標準タイプから始めて、必要に応じて幅広タイプや幅狭タイプを買い足していくと良いでしょう。
自分の体型や着物の種類に合わせて、最適な幅のさらしを選びましょう。
5.さらしのお手入れ方法
さらしは適切なお手入れで長持ちさせることができます。素材ごとのお手入れ方法を押さえて、清潔に使いましょう。
洗濯方法
- モスリン・和晒:どちらもデリケートな素材なので、手洗いかネット使用で優しく洗いましょう。ぬるま湯で押し洗いし、柔軟剤や蛍光増白剤は避けてください。和晒は特に肌触りにこだわりがあるため、慎重に扱いましょう。
- ネル・晒木綿:ネルは摩擦で毛羽立ちやすいため、単独でネットに入れて洗います。晒木綿は煮沸消毒が可能ですが、通常の洗濯機洗いも問題ありません。どちらも柔軟剤を控えめに使用し、やさしく洗ってください。
保管方法
- モスリン・和晒:風通しの良い乾燥した場所で保管し、湿気を避けましょう。和晒は特に高級素材なので、桐のタンスや衣装ケースでの保管が理想的です。アイロンが必要な場合は低温で当て布を使用します。
- ネル・晒木綿:両素材とも湿気に弱いため、風通しの良い場所でしっかり乾かしてから収納します。ネルは重みがあるため、たとう紙に包んで桐のタンスで保管するのが最適です。
6.まとめ
この記事では、着付けに欠かせないさらしについて、種類、役割、巻き方、選び方、お手入れ方法、注意点まで詳しく解説しました。
モスリン、ネル、晒木綿、和晒など、それぞれの素材の特徴を理解し、用途に合ったさらしを選ぶことが大切です。
また、胸元や腰回りなど、補正したい部分に合わせた巻き方をマスターすることで、美しい着姿を実現できます。適切な洗濯と保管方法で、さらしを長く愛用しましょう。
さらしを正しく使い、快適で美しい着物姿を楽しみましょう。
まるやま・京彩グループでは、初心者向けの着付け教室を開催しています。
経験豊富な講師が、やさしく丁寧にサポートしますので、安心して学べます。
少人数制なので、気軽に質問でき、手元の動きもしっかり確認できますよ。
まずは無料体験レッスンで、あなたのペースで楽しく学んでみませんか?
まるやま・京彩グループでは、着物好きの皆さんがステキな着物ライフを送れるよう、お役立ち情報を発信していきます。
着物の選び方や着こなしについて、もっと詳しく知りたい方は、ぜひまるやま・京彩グループの着付け教室、無料体験レッスンにお越しください。
経験豊富なスタッフが、あなたにぴったりの着物選びをお手伝いします。