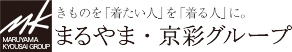着方レッスンコラム着方レッスンコラム
苦しくない!着崩れない!自分でできる着付け&帯結び
2025.05.29

こんにちは!「着たい人を、着る人に」まるやま・京彩グループです。
着物を自分で着られるようになると、もっと気軽に和装を楽しめるようになります。
ちょっとしたお出かけや記念日、家族のイベントなど、特別な日も自分の手で準備できれば、時間にもお金にも余裕が生まれます。着物が「特別な装い」から「日常の選択肢」へと変わる、そんな瞬間を体験してみませんか?
この記事では、初心者の方でも安心して挑戦できるよう、必要な道具、苦しくない着付けのコツ、基本的な帯結び、そしてよくある失敗とその対策まで、写真や動画なしでも分かるよう丁寧に解説します。
目次 [hide]
1.自分で着付けをするメリット

着付けを自分で行えるようになると、時間・費用・場所の自由度が大きく広がります。
まず、着付け師に依頼する必要がないため、自分のタイミングで準備ができます。早朝の予定や急なイベントにも対応できる柔軟さは、自分でできるからこその魅力です。
また、着付け代や教室の費用が不要になれば、着物や帯、小物の購入に充てる余裕も生まれます。
さらに、旅行先やイベント会場など、場所を選ばずに着物を楽しめるようになるのも大きなメリットです。
一度習得すれば、自分のためだけでなく家族や友人に着せてあげる機会も増え、和装の楽しみが広がります。
2.着付け練習を始める前に揃えておきたいもの

以下のアイテムを揃えておくと、安心して練習に取り組めます。
- 着物:初心者には扱いやすい洗えるポリエステル素材の着物がおすすめです。お手入れも簡単で、気軽に練習できます。
- 帯:名古屋帯や半幅帯、袋帯など、用途や場面に応じて使い分けることができます。帯は着物の印象を大きく左右する重要なアイテムです。
- 和装下着:長襦袢、肌襦袢、裾よけなどの和装下着は、着物を美しく着こなすために欠かせません。
- 足袋:白足袋が基本で、着物の雰囲気を引き締めます。
- 腰紐:腰紐は3本程度、伊達締めは補正用の幅広い紐で、着崩れを防ぐ役割を果たします。
- 伊達締め:着物の前をしっかりと留め、形を整える幅広い紐です。
- 帯板、帯枕:帯の形を整え、綺麗なシルエットを作るための小物です。
- 帯揚げ、帯締め:帯を固定するとともに、装飾としても重要な役割を担います。
これらのアイテムを揃えることで、着物の練習をより快適に、そして美しく進めることができます。
3.苦しくない着付けのコツ

「着物は苦しい」と感じる方の多くは、締める場所や力加減を間違えているケースがほとんどです。
衣紋の抜き方
首の後ろに指2〜3本分のゆとりをもたせると、窮屈に見えず首元がすっきりと綺麗に見えます。
おはしょりの整え方
帯の下から出る折り返し部分を左右均等に整えることで、着姿全体がバランスよく見えます。
体型に合わせた補正
タオルなどを使ってウエストやヒップのくぼみをなだらかにすることで、帯がずれにくくなり一日中快適に過ごせます。
無理に締めるのではなく、必要な部分を適度に支えるのがコツです。
4.初心者でもできる帯結び
名古屋帯の一重太鼓
帯を体に2周巻き、背中で山折りにした帯を帯枕で支え、帯揚げと帯締めで形を整えるスタイル。フォーマルからカジュアルまで幅広く使えます。
半幅帯の文庫結び
軽くて柔らかい半幅帯は初心者に最適。体に巻いたあと羽根を左右に作り、真ん中を帯で結んで形を整えます。
浴衣や普段着にもぴったりです。
どちらも動画がなくても、手順をメモしながらゆっくり練習することで習得できます。
5.練習の進め方
最初から完璧を目指すのではなく、段階的に進めるのがおすすめです。
- 肌襦袢・長襦袢の着方をマスターする
- 着物の裾合わせ・おはしょりの調整に慣れる
- 最後に帯結びを練習する
時間をかけて手の動きを覚えていくことで、自然と流れが身につきます。慣れてきたら、出かける直前に着る練習をしておくと本番でも焦らずに済みます。
6.よくある失敗とその対策

衣紋が詰まりすぎる
→ 襟を抜く位置が浅いと苦しそうな印象に。指2〜3本分の空間を目安に調整しましょう。
おはしょりが左右で不揃い
→ 帯を巻く前に鏡で左右をチェックし、整える癖をつけると改善します。
帯が緩んで形が崩れる
→ 最初の一巻きはしっかりと締め、帯枕・帯揚げ・帯締めで丁寧に固定しましょう。
時間が経つと着崩れる
→ タオルを使った補正と、正しい腰紐・伊達締めの位置で着姿が安定します。
道具の使い方が分からなくなる
→ 最初はすべてを覚えようとせず、少しずつ使いながら慣れていくのが◎。簡単な手順メモを準備しておくと安心です
失敗しながら覚えるのも着物の楽しさのひとつ。繰り返すうちに、だんだんと自信が持てるようになります。
7.まとめ

着物は特別な日だけのものではありません。
たとえば、初詣やお花見、美術館デートやランチ会など、「ちょっとおしゃれしたいな」と思う日にこそぴったりです。洋服のように、気軽に選べる一枚があれば、日常に彩りが加わります。
自分で着付けができるようになれば、天気や気分に合わせて自由にコーディネートを楽しむことができます。
文章や動画で学ぶのも素敵ですが、「細かいところを見てほしい」「やり方が合っているか不安」という方は、ぜひ着付け教室をご利用ください。
まるやま・京彩グループでは、初心者向けの着付け教室を開催しています。
受講前に体験できる無料レッスンもご用意しております。
- 自分で着物を着てみたい方
- イベントに向けて練習したい方
- 和装の基本からしっかり学びたい方
講師がやさしく丁寧にサポートいたします。少人数制で質問もしやすく、手元の動きまでしっかり確認できるのが魅力です。
この記事が、あなたの着物ライフの第一歩となれば幸いです。
まるやま・京彩グループでは、着物好きの皆さんがステキな着物ライフを送れるよう、お役立ち情報を発信していきます。
着物の選び方や着こなしについて、もっと詳しく知りたい方は、ぜひまるやま・京彩グループの着付け教室、無料体験レッスンにお越しください。
経験豊富なスタッフが、あなたにぴったりの着物選びをお手伝いします。